
今日はどんなテーマでしょうか?

はい、今日は「最低限覚えることは?」というテーマです。

局免許、従事者免許を取った際、結構学んだような気がします。

覚えるという意味では従事者免許を取得するときに結構覚える必要がありましたね。
実際は法令などは調べれば出てきますので、それらについてはこういうのがあったな程度で充分だと思います。
では、最低限必要なものを挙げるとすると
- 電気はうかつに触れると生命に関わる可能性がある
- 電波は誰が受信しているか分からない
- 電波は予期せぬ機器への予期せぬ影響を及ぼす可能性がある
- いろんな機器を使うので火災により注意する必要がある
- アンテナを上げるなら台風や落雷等に備える必要がある
まずはこんなところでしょうか。

私の知っているより電気は怖いものですね。
それぞれについてどう対策したらいいか、どのような例があるか解説をお願いします。
1. 電気はうかつに触れると生命に関わる可能性がある

それぞれ直流と交流で危ない電圧があったような気がします。
それでも、例えばモバイルバッテリーをふろ場に持ち込んで感電などといったことも聞きますし、やはりいくつか条件はあるみたいですね。

電圧の値としては交流で40V、直流で70Vを越えるものに触れると危険であるとされていますね。もちろん乾燥の具合にもよるのですが、大切なのは何ボルトであっても直接触れない、必ず電源を切って放電させてから、というところです。
2. 電波は誰が受信しているか分からない

「ラジオ」とかその例ですね。AMでも遠くの局が聞こえたりしたことがあります。
あとは特小のトランシーバーで遊んでた頃にも工事現場の人の声が入ってきたりしてましたね。

これはラジオの例も含め、誰が聞いているか分からないので誰に聞かれても不都合のない内容でなければならない、というソフト的な点に留意いただきたいですね。
3. 電波は予期せぬ機器への予期せぬ影響を及ぼす可能性がある

D級アンプの電源を入れているとラジオに雑音が入ったりしましたね。

そうなんです。
細かく言うと受信しているだけでも障害を及ぼす可能性はあるのですが、明示的に送信するわけですから受信だけの時とは比較にならない電界強度ということで、必ず何らかの影響はあると思っておいた方がいいです。正式に免許を得ているとは言え、電波を発射する限りはその行為に責任が伴う、というところをしっかり認識しておく必要がありますね。もちろん必ず対策は可能ですから、尻込みしてしまう必要はありません。
4. いろんな機器を使うので火災により注意する必要がある

例えばオームの法則により無線機でよく使われる12Vと100Vでは大きな違いがあると知りました。

これについては世間で言われているのと同様、いわゆるタコ足配線やトラッキング火災、あるいはコードを束ねて使用しないなど一般的な内容にしっかり注意していれば良いのではないかと思います。あとやってしまいがちなのがハンダごての抜き忘れ。今は切り忘れタイマ付きのものもありますが、自作派は特に要注意です。
5. アンテナを上げるなら台風や落雷等に備える必要がある

これは避雷器とかで対策できそうですね。

そうなんですが実はこれ、結構難しいんです。僕は無線をしないときは常にアンテナからのケーブルを外しておくようにしているのですが、それにしたって直雷(雷が直接落ちること)を受けてしまうと何らかの影響があるかも知れません。また幸い直雷にもかかわらず被害がなくても、それによる誘導雷でご近所の機器に不具合がでた場合、あなたのところで大きなアンテナを上げているからこちらの機器が損傷した、等と言われてしまうことも考えられます。そのあたりは技術的なこともさることながら、普段からのご近所づきあいなどソフト的なことが大切になってきます。

ありがとうございます。
それぞれでの対応がよくわかりました。
それぞれまとめると、
1.機器を触るときは放電を確実にする
2.誰が聞いてもいい内容にする
3.送信するときは対策を十分に
4.トラッキング火災やジュール熱による火災などに気を付けておく
5.ご近所づきあいを大切にする
これらを最低限覚えておきますね。
本日はどうもありがとうございました。

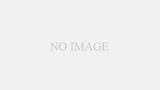
コメント